川越市保健所医療講演会 2007年2月11日
「膠原病と痛みについて」
安藤医院 安藤聡一郎
 はじめに
はじめに
本日は、膠原病、関節リウマチ患者さんのために、痛みについてお話させていただきます。痛みがなぜ起こるのか、その痛みはいかにして和らげることができるのか、といったことをお話したいと思います。
たとえば、リウマチ白書の「リウマチによる職業生活への影響」のデータなどを見ますと、多くのリウマチ患者さんが、リウマチになったために仕事を制限したり、やめたりしなければならなくなっていることがわかります。ここにお集まりの患者さんの中にもそのような悩みを抱えていらっしゃる方は多いことでしょう。
そのデータには示されていませんが、そのようになってしまう原因はいろいろあるだろうと思います。通院が必要だから、とか、通勤ができなくなったからとかいろいろな原因があると思いますが、多かれ少なかれ、痛みがあるために制限せざるを得ないとか、痛みが強くなりそうでどうしても前向きになれないといったことはあるのではないでしょうか。「痛みが消えてくれたら、」あるいは、「もう少しコントロールできたら・・・」というのは、痛みを抱えたリウマチ患者さん、膠原病患者さんの共通の願いではないかと思います。
今日はまず、痛みがなぜ起こるのか、という話をさせていただき、痛みに対する治療法、対処法を紹介し、皆さんの療養の助けになればと思います。
 痛みのメカニズム
痛みのメカニズム
痛みはどこで感じるかというと、脳で感じるわけです。たとえば手の痛みが脳にどうやって伝わるかというと、神経を通じて感じます。神経は全身に張り巡らされていて、最終的には脳に伝わります。ですから、体の神経が痛み刺激を受けると、その部分の刺激が痛みとして脳で感じるのです。では、神経はどのように刺激を受けるのでしょう。それは、さまざまな化学物質が刺激を与えます。体の中で、そのような化学物質(わかりやすくするために「痛み物質」といいましょう)が作られると、その化学物質が神経を刺激し、神経が脳に信号を送り、痛みを感じます。そのような痛み物質は、炎症が起こると作られます。炎症というのは、本来、身体を病原体などから守るときに起こる反応です。たとえば、手に傷ができてそこにバイキンが入ったとしましょう。するとそこは赤く腫れ、熱を持ち、痛みが起こるでしょう。そこで起きていることは、バイキンを身体から排除するために、白血球やリンパ球やさまざまな生体物質がバイキンと戦っていることなのです。そのときに産生される痛み物質が神経を刺激して、痛みとして感じるのです。
リウマチや膠原病患者さんの身体の中では、病原体などが入ったわけではなく、何らかの理由で炎症がおきてしまうのです。そして、リウマチ患者さんの場合であれば、関節で炎症性サイトカインと呼ばれるTNF-α、IL-1、IL-6などが様々な細胞から作られ、それらの物質がまた他の炎症性細胞を刺激し、プロスタグランジンなどの物質が作られます。これが痛み物質として神経を刺激し、その信号が脳に伝わり、「痛い」と感じるのです。
ですから、痛みの薬物治療には、これから述べますように、炎症そのものを鎮めること、痛み物質であるプロスタグランジンが作られないようにすること、神経をブロックして、痛みを感じなくすること、などがあります。
また、身体の痛みの感じ方には、「閾値」というものがあります。あるレベルまでは痛いと感じないが、そのレベルを超えると痛いと感じる、という境界線があり、それを閾値といいます。同じ刺激でも人それぞれ痛さとしての感じ方はさまざまです。それは、閾値が人によって多少違うからです。ですから、痛みに対する対処方法として、痛みの閾値を上げる、という方法も考えられるわけです。たとえば、鍼や灸の効果はそのような効果なのではないかという説もあります。また、さまざまなリラクゼーション、アロマセラピーとか、音楽などに痛みを和らげる効果があるのもそのような効果によるのではないかと考えられます。図に示すと次のようになります。器からこぼれた水が痛みを表します。器に注ぎ込む水が痛み物質です。痛み物質が多いと器からこぼれる水も増え、強い痛みを感じます。痛みに対する治療は、図に示したように、原因に近いところを治療し、痛み物質が作られないようにする、痛みを伝える神経をブロックして痛みを感じなくする、といったほうほうが考えられます。そして、痛みの閾値を上げる、つまり図でいうと器を大きくして痛み物質が増えてもこぼれなくする、といった方法もあるでしょう。
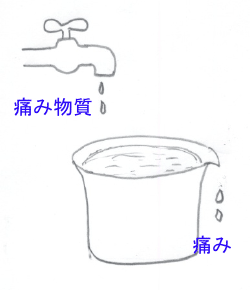
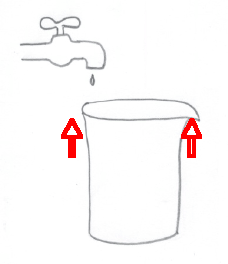
(図:左:痛みと痛みの治療薬、右:痛みの閾値の関係、著者オリジナル)
 痛みへの対処
痛みへの対処
- 薬物療法
- 非ステロイド消炎鎮痛剤
- ステロイド
- 抗リウマチ薬、免疫抑制剤、生物学的製剤
- 非薬物療法
 非ステロイド消炎鎮痛剤について
非ステロイド消炎鎮痛剤について
- 炎症物質であるプロスタグランジンの産生を抑制する
- 分類
- カルボン酸系、酢酸系、プロピオン酸系
- 半減期による違い
- 飲み薬、 坐薬、 シップ、 軟膏
- 副作用:胃腸障害、腎障害、 薬剤相互作用
- 副作用対策
- 薬の飲み方の工夫
- 空腹時を避け、牛乳で飲む
- 明け方痛みが強いときは坐薬を使う
- 内臓障害の定期的チェック
 ステロイドについて
ステロイドについて
- 副腎皮質ホルモンである
- 生体内の物質であるが、様々な作用を有するため、副作用も問題となる
- 抗炎症作用と免疫抑制作用を有する
- 投与方法
- 効果はかなりよい
- 長期間の投与では副作用が問題
- ステロイドの副作用対策
- カロリーのとりすぎに注意
- ステロイドによる肥満、糖尿病、高脂血症に対して
- カルシウムをとるようにする
- カリウムをとるようにする
- 感染症予防
- 自己判断で中止しない
 抗リウマチ薬、免疫抑制剤、生物学的製剤について
抗リウマチ薬、免疫抑制剤、生物学的製剤について
- 関節リウマチ、膠原病の原因に近いところで抑える治療で、ここ数年でかなり進歩してきています。これについては今回は割愛させていただきます。詳しい本(参考文献4)などもありますのでそちらをご参照ください。
 非薬物療法
非薬物療法
 代替医療について
代替医療について
- 鍼、灸、指圧、アロマセラピー、音楽療法など
- 痛みに対して、「閾値」を上げ、痛みの感じ方を和らげる効果があるといわれています。
- 局所の血流をよくし、痛みを和らげる効果もあります。
- 東洋医学に関しては今の科学ではまだ未解決の部分も多くあるようです。
- ご自分にあった治療であれば取り入れてみるのがよいでしょう
 セルフマネージメント
セルフマネージメント
- アメリカスタンフォード大学で開発されたもので、病気とどう向き合い、どうやってさまざまな困難を乗り越えていくか、治療の効果を最大限にあげるには、といったことを、グループで意見を出し合い考えていく方法です。
- 最近日本でも注目されるようになりました
- 埼玉県膠原病友の会でも行っていますのでお問い合わせ下さい
- この中で、痛みは自分が管理する、といったことが強調されています
セルフマネージメントによる、痛みの管理の手法を紹介します。
痛みの自己管理者となるために
- 何をしたいか(目標を具体的にたてる)
- そのために必要なステップは
- 短期間の実行計画を立てる
- 実行プランの実施
- 結果をチェック
- 途中での修正を加える
1. 何をしたいか(目標を具体的にたてる)
- やりたいことをすべて挙げてみる
- たとえば
- 娘の家の12段の階段を上れるようになりたい
- 体重を減らしたい
- 時間はかかるかもしれませんが、”夢”のように考えず、”やってみなければわからない”、と考えてみましょう
2.そのために必要なステップは
- 目標達成には様々な方法があるはずです
- 例: 階段を上れるようになりたい
- ゆっくり歩くことからはじめ、膝の筋肉トレーニングを取り入れ、杖の使い方を覚え、 毎日少しずつ階段を上ってみる
- 例: 体重を減らしたい
- 間食を やめる、デザートは食べない、揚げ物は食べない、運動を取り入れる
- 目標達成のための方法
- 目標達成のための方法はたくさんあるはずです
- まずそれらを書き出してみましょう
- 方法が思い浮かばなかったら、友達、家族、医師、看護師、 理学療法士などのまわりの協力者に聞いてみましょう
- 相談者を持つことは大切です
3.短期間の実行計画を立てる
- “ 短期間 ” の実行計画= 翌週までに終えられる計画を
- “ 今週 ” 行うことを決める
- 階段を3段上る、間食を3日間やめてみる、週2 回は お菓子を食べない、 など
- 目標にあった計画を立てる
- 目標にあった計画を立てるために
- やろうと思っていることは何かを明確に
- どのくらいするつもりか
- いつするのか
- どのくらいの頻度で行うのか
- 実行計画を立てるコツ
- 今できることから始める
- ゆっくり始める
- 休養日は必ず設ける
- 毎日ではなく、週3回〜5回
- 実行計画を立てたら、それが本当に実行可能か考えてみる
- 0を実行不可能と思える場合、10が自信を持ってできそうな場合、として7以上ならよい。7以下の場合は計画の見直しを
- 計画をカレンダーなどに記す
4.実行プランの実施
- 家族や友人に、計画がうまくいっているか聞いてみる
- 進捗状況を報告したり、聞いてみることはモチベーションを高めるのに役立つ
- 毎日の行動を見失わないこと
- ノートに記録しておく
- あとで問題解決に役立つ
- 例:階段
- ノートにできなかった理由(言い訳)を書いておく
- 転倒が怖い、そのとき誰もいなかったら・・・と思うと
- 杖を使ってみよう、誰かについてもらおう、などの解決策
5.結果をチェック
- 毎週、目標にどのくらい近づいたか考えてみる
- すこし長く歩けるようになりましたか?体重は減りましたか?疲れにくくなりましたか?
- 振り返ってみることはとても大切
- 昨日と今日では違いがなくても、先週と今週では少し変化しているはず
- 問題があれば誰かに相談を
- しかし、相談相手は問題解決をしてくれるわけではない、助けてくれるだけ
6.修正を加える
- 何事も最初からうまくはいきません
- うまくいかなくても、決してあきらめてはいけません
- ほかの方法を考えて見ましょう、計画を修正しましょう、もう少し時間をかけてみましょう
- やめないで、助けを借りましょう
 日常生活の工夫
日常生活の工夫
- 日常生活でいろいろな工夫をすることで、痛みを和らげることができます。また、それは関節の保護にもつながります
- 安静と運動のバランスが大切です
- 安静のとり方
- 薄い敷き布団を使いマットレスや高い枕は使わない(腰が沈み込んだり、首が曲がりすぎるのはよくない)
- ベッドは硬いものを
- 頭を床におしつけ、背筋が伸びた状態を5分間続け、その後は楽な姿勢で休む
- 仕事の合間の休息
- 椅子で休むときは両足底が床につき、背筋がまっすぐに伸びる椅子を使う
- 柔らかいソファ−はよくない
- 関節拘縮予防、筋力低下予防のため少しでも動かすようにしましょう
 リウマチ体操
リウマチ体操
- 関節痛を和らげ、筋肉を強くするために
- 普通、一日2〜3回、特に温浴のあとで行うと効果的です。
- 運動のあと、痛みが増しても、1〜2時間で元に戻るようなら続けても構いません
- ご自分の症状を調べながら適度に行うようにして下さい。
- 関節リウマチ患者さんに限らず、取り入れるとよいでしょう
リウマチ体操は、参考文献1や以下のホームページなどが参考になります
リウマチ情報センターのホームページ
 痛みに対する考え方
痛みに対する考え方
- よくある質問
- 温めた方がいいいのですか?冷やした方がいいのですか?
- 動かした方がいいのですか?動かさない方がいいのですか?
- 炎症の強い時期(腫れ、熱感がある)は動かさない。痛みに対して冷やすのはよい。温めない方がよい。
- 炎症が軽くなってきたら温、冷どちらでもよい。他動的に動かす。痛みが残るようならやりすぎ。
- 炎症がなくなったら(痛みは軽くなっている)自動的に動かす。リウマチ体操を積極的に行う。
 リウマチの関節保護
リウマチの関節保護
- 一日10〜12時間の休養、昼寝を含む
- 努力しすぎない
- 同じ姿勢を長く続けない
- 以下の場合は運動量過多。翌日は少なめに
- 運動中、作業中に痛みがでる、
- 運動中、作業中に痛みが増す、
- 運動後、作業後に痛みが1時間以上続く
- 変形を増長させるような方法、肢位をとらない
- 毎日適切な運動
- 1日2回最大可動域まで動かす
- 自助具の使用
 日常生活動作の工夫の具体例
日常生活動作の工夫の具体例
- 急須は手のひらにかけ、もう一方で蓋を押さえる
- 鍋の取っ手は指で持たず、手袋を使って手全体で持つように
- コ−ヒ−カップは両手で、一方は底から支えるように
- 鞄は腕にかけるかショルダ−に。キャリアー、ワゴンなどを使いましょう
- ぞうきんがけの工夫
- ぞうきんがけは親指側へ、小指側にかけると手首に負担がかかる
- ぞうきんやタオルを絞るときの工夫
- ぞうきん絞りは水道の蛇口をつかって両手で
- 冷蔵庫を開けるのに、紐を取っ手にかけ、腕で引っ張るなど工夫しましょう
- いすから立ち上がるときの手の使い方にも気をつけましょう。手のひらを使いましょう
- 引き出しを閉めるのに腰を使ってしまいましょう(ちょっとお行儀悪いと感じるかもしれませんが)
- ハンガーに服をかけるときは両手で
- 仕事の机は必要なものにすぐに手が届くように工夫しましょう。
- パソコンのマウスもさまざまな形のものがあります。手に優しいものを選びましょう。手首への負担を考えて。
- 書見台は首の痛みを防ぐのに役立ちます
- 書類の引き出しなどは、下に足台を置いて片足を少し前に出して高くするようにすると腰痛予防になります
- いすからの立ち上がりは、浅めに座った位置から、片足を前に出して、片足は膝より後ろにして、手に重心をかけすぎないようにして立ち上がりましょう。少し反動をつけるのもよいでしょう。腰痛の予防になります。
- 床のものを持ち上げるときは、しゃがんで抱えて持ち上げましょう
- キッチンも、必要なものはワゴンにまとめたり、すぐに手の届く位置にまとめるようにしましょう
- さまざまな便利グッズを利用しましょう。
- 自助具として普及しているものもあります。日本リウマチ友の会ホームページにいくつか紹介されています。
 外反母趾対策
外反母趾対策
- 外反母趾も痛み出すとなかなかやっかいなものです。外反母趾の予防と治療に大切なのは靴の選択です。足の裏は、アーチ構造といって、縦のアーチ、横のアーチがあります。縦のアーチは、足を縦に見て、土踏まずのところでふくらんでいる構造、横のアーチは、横に見て、足の指の付け根の中心がふくらんでいる構造です。このアーチ構造を保つことが外反母趾の予防と治療に重要です。
- 靴の選択:幅の広い、踵の低めのもの。はな緒のあるようなもの。ア−チのあるもの(土踏まずのところが少し盛り上がっているものがよいでしょう)。パットを貼るなどしてもよいでしょう。
- 足の体操
- 足の指の付け根、すね、ふくらはぎをマッサージすることは大切です
- 足のジャンケンも有効です。左からグー、チョキ、パー。
- 当院のホームページでも以前紹介しました。こちらをどうぞ。
 まとめ
まとめ
- 膠原病の痛みの原因は様々です。
- 炎症による痛みに対しては、炎症の元を抑える治療(ステロイド、抗リウマチ薬、免疫抑制剤、生物学的製剤)、炎症による痛み物質を抑える治療(非ステロイド消炎鎮痛剤、ステロイド)などの薬物治療があります。
- 薬を使用する際は、薬の特徴を理解し、副作用対策をしっかり行いましょう。
- 非薬物療法として、鍼、灸、指圧、アロマセラピーなどもある程度の効果はありますが、原因治療ではない点は注意して下さい
- セルフマネージメントの手法も、痛みを克服して目標を達成するのに有効です。
- 日常生活の工夫で痛みを和らげることができ、関節の保護にもなります。
<参考文献、ホームページなど>
- 膠原病を克服する、橋本博史著、保健同人社
- The Arthritis Help Book, Kate Lorig, R. N., James F. Fries, Lifelong Books
- リウマチノート、松山赤十字病院リウマチセンター編、エーザイのパンフレット
- 膠原病・リウマチは治る、竹内勤著、文春新書
- 日本リウマチ友の会のホームページ(リウマチ白書のデータ、自助具の紹介など)
- リウマチ情報センターのホームページ(リウマチ体操やQ&Aなど)
- 埼玉県膠原病友の会(セルフマネージメントを取り入れています。住所:330-8522 埼玉県さいたま市浦和区大原3−10−1埼玉県障害者交流センター内TEL:048-832-8495)
- 日本慢性疾患セルフマネージメント協会のホームページ(セルフマネージメントに関する解説、ワークショップの案内など)
<質疑応答より>
- SLEですが、治療薬と骨粗鬆症との関連について教えて下さい
- ステロイドを服用していると骨粗鬆症になりやすくなります。その理由は、カルシウムの吸収が低下することと、骨を削り取る働きの破骨細胞の働きが活発になるためです。したがって、骨粗鬆症の予防には、カルシウムを多くとること、ビタミンDを多くとること、ビタミンDを活性化するため日光に当たることなどが重要です。日光については、日光過敏症のある場合はよくありませんので主治医によく確認して下さい。また、ビスフォスフォネートと呼ばれる薬がステロイドによる骨粗鬆症にもよく効きます。長期間ステロイドを飲む方は併用した方がよいでしょう。カルシウムとビタミンDは食べ物からとるとすると、カルシウムは乳製品、小魚類から、ビタミンDは干し椎茸などからということになりますが、サプリメントや処方薬としてとった方が楽かもしれません。主治医によくご確認下さい」。
- 強皮症ですが、指先の痛みはなぜ起こるのでしょうか?
- 強皮症の場合は、指先の血管が敏感になっていて、ちょっとした温度の低下や精神的な緊張でも血管が収縮して血流が低下してしまいます。それによって指先が白くなることをレイノー現象と言います。そのときは指先の血流が低下するために痛くなることが多いと思います。痛みはそのようなメカニズムで起きますので、指先を冷やさないようによく暖めることが大切です。
- 関節リウマチですが、ミノマイシンという抗生物質を飲むと痛みが軽くなります。これはどうしてなのでしょうか?
- 関節リウマチの原因はまだよくわかっていませんが、何らかの感染症の関与が指摘されています。様々な病原菌の中でも、普通の細菌ではなくクラミジアやマイコプラズマといった病原体の仲間の病原体が関与している患者さんもいるのではないかと言われています。その根拠は、ミノマイシンという、一般細菌よりはそれらの病原体によく効く抗生物質を服用するとリウマチの症状もよくなる人もいる、と言う事実にもとづいています。アメリカではミノマイシンもリウマチの治療薬として認められています。しかし、問題は、すべてのリウマチ患者さんにあてはまるわけではないことと、服用をやめれば症状が再び出現することと、この薬によって肝障害の副作用が起きやすいといったことがあります。
- リウマチと強皮症を合併しています。薬は?
- リウマチと強皮症を合併している患者さんもいらっしゃいます。リウマチの治療が中心となることが多いと思いますが、強皮症の程度によっては強皮症の治療も必要になります。強皮症を合併したリウマチだから何か特別の薬があるということはありません。病状に応じた治療を行います。ただ、特に行ってほしいのは、手の温浴です。これはリウマチの関節病変に対しても有効ですし、強皮症にも有効です。
![]() はじめに
はじめに![]() 痛みのメカニズム
痛みのメカニズム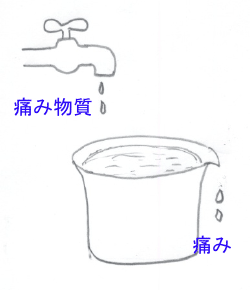
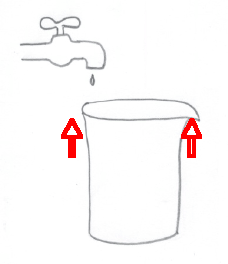
![]() 痛みへの対処
痛みへの対処![]() 非ステロイド消炎鎮痛剤について
非ステロイド消炎鎮痛剤について![]() ステロイドについて
ステロイドについて![]() 抗リウマチ薬、免疫抑制剤、生物学的製剤について
抗リウマチ薬、免疫抑制剤、生物学的製剤について![]() 非薬物療法
非薬物療法![]() 代替医療について
代替医療について![]() セルフマネージメント
セルフマネージメント![]() 日常生活の工夫
日常生活の工夫![]() リウマチ体操
リウマチ体操![]() 痛みに対する考え方
痛みに対する考え方![]() リウマチの関節保護
リウマチの関節保護![]() 日常生活動作の工夫の具体例
日常生活動作の工夫の具体例![]() 外反母趾対策
外反母趾対策![]() まとめ
まとめ