第29回健康講座 骨粗鬆症について
 本日の予定
本日の予定
- 骨粗鬆症とは
- 骨の健康度チェック
- 骨を強くするために
- 転倒について
- 転倒予防のために
|
 骨粗鬆症とは
骨粗鬆症とは
- 定義:低骨量と骨の微細構造の劣化により骨の脆弱性が増し、骨折しやすくなった全身性の骨疾患
- つまり、骨粗鬆症になると、ちょっとしたことで骨折することがあります。
 脆弱性骨折とは
脆弱性骨折とは
- 骨密度の低下が原因で起きる骨折
- 脊椎(背骨)
- 大腿骨頚部(足の付け根)
- とう骨遠位端(手首)
- などに軽い外力で生じた骨折
- 特に、脊椎の骨折(圧迫骨折)、大腿骨頸部骨折は寝たきりの原因になるおそれがあります
 骨の健康度チェック
骨の健康度チェック
- このリンク先のホームページで骨の丈夫さをチェックしてみましょう
- 「丈夫な骨で生き生きライフ」骨の丈夫さチェック 骨粗鬆症財団より
 骨密度の変化
骨密度の変化
- 骨の強さは18歳ごろにピークとなり、以後徐々に減少していきます(生理的現象)
- 特に女性では、閉経後に骨密度の低下が進みます
- 後で述べるような危険因子のある方の場合は、さらに速く進み、骨粗鬆症になることがあります
 骨密度からみた骨粗鬆症
骨密度からみた骨粗鬆症
- 若い人の平均骨密度(YAM)の70%未満を骨粗鬆症と定義しています
- それは、脆弱性骨折がおきやすくなるレベルと考えられています
 骨はどうして弱くなるのでしょうか
骨はどうして弱くなるのでしょうか
- 骨は石のような固まりではなく、生きているのです
- 骨の吸収(古い部分を取り除く)と形成(新たな骨を補強)の新陳代謝が繰り返されているのです。これをリモデリングといいます
- 骨の吸収に約40日、形成に3〜4ヶ月かかる=骨が生まれ変わるのに約6ヶ月かかります
- この骨吸収と骨形成のバランスが崩れ、骨吸収が亢進すると骨は弱くなるのです
骨の内部の骨梁といわれる、骨の”骨組み”を模式的に示すと下図のようになります。このように、無数の柱が骨を支えているのです。
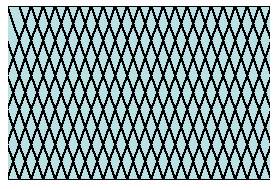
ところが、骨粗鬆症になると、下図のように柱である骨梁一本一本が、細くなり、また、数も減ってしまうのです。そうすると骨はもろくなってしまい、ちょっとした力が加わると(転んだときなどに)骨折が起きてしまうのです。
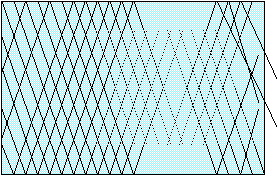
 どんな場合に骨は弱くなるのでしょうか
どんな場合に骨は弱くなるのでしょうか
- カルシウム、マグネシウムなどが不足したとき
- ホルモンの変化(加齢)
- 運動不足
以上のような場合に骨は弱くなります。他にもいくつかの要素が知られており、骨粗鬆症の危険因子として次のようなものが指摘されています。
 骨粗鬆症の危険因子として次のようなものがあります
骨粗鬆症の危険因子として次のようなものがあります
- 食生活では
- カルシウム不足
- 偏食(無理なダイエット)
- 食塩の多量摂取
- 高蛋白、高リン食
- 嗜好品では
- アルコールの多量摂取
- ヘビースモーカー
- カフェインの多量摂取
- 薬剤では
- 運動に関して
- 身体的な要素
- 高年齢
- 女性である
- やせている
- 閉経がはやい
- 人工閉経(卵巣摘出術など)
- 家族に骨粗鬆症の人がいる
- 出産歴がない
- 授乳
 骨粗鬆症、骨折予防のために
骨粗鬆症、骨折予防のために
 まず、食事のポイントについてみていきましょう。
まず、食事のポイントについてみていきましょう。
ポイントは、カルシウムとビタミンDを多くとることです・
 一日のカルシウム摂取量
一日のカルシウム摂取量
- 乳幼児期400mg
- 学童・青年期500〜900mg
- 成人男女:600mg
- 妊娠・授乳期:1000〜1100mg
- 高齢者:600mg
- 骨粗鬆症の予防には800mg
- 今までの食事に200mgのカルシウム追加を心がけましょう
 カルシウム
カルシウム
- カルシウムを多く含む食材
- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)
- 大豆製品(豆腐、納豆)
- 小魚、海草類(ひじき、わかめ、のり)
- 緑黄色野菜(小松菜、チンゲンサイ)
- カルシウムの吸収率が食材によって異なります
- 牛乳、乳製品>大豆製品>小魚類>野菜
- 吸収率も考慮してメニューを考えましょう

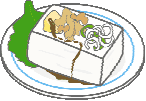

 ビタミンD
ビタミンD
- ビタミンDはカルシウムの吸収を助けます
- ビタミンDは皮下に集まり、日光に当たると活性化されます
- ビタミンDの多い食品:鮭、ニシン、干し椎茸、カレイ、ウナギ、煮干し、サンマなど
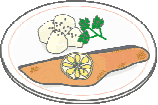
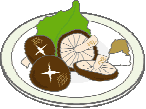
 マグネシウム
マグネシウム
- マグネシウムも骨の材料となります
- カルシウム2:マグネシウム1の割合でとることが理想的とされています
- マグネシウムの多い食品:アーモンド、カシューナッツ、大豆、落花生、ひじき、納豆、ほうれん草、インゲン豆、鰹、青のり、小豆、トウモロコシ、枝豆、バナナ、ココア、おかひじき、カマス、サンマ、あじ、小麦麦芽など

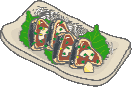
 塩分について
塩分について
- 塩分をとりすぎると、尿へのカルシウム排泄が増えるので、塩分は控えめにしましょう。
 アルコール、喫煙について
アルコール、喫煙について
- アルコールの飲みすぎはカルシウムの吸収を低下させます
- 喫煙もカルシウムの吸収を悪くします


 運動について
運動について
 運動の骨粗鬆症予防効果
運動の骨粗鬆症予防効果
- 次のような統計があります
- 1日の歩行数と骨密度が相関=よく歩く人ほど骨は強い
- ゲートボール愛好家は同年齢の人より橈骨骨密度が20〜30%高い
- 運動教室に1年間参加した男女は平均6%前後の骨密度が増加
- 運動が骨粗鬆症の予防に効果があることがわかると思います
 運動療法の実際
運動療法の実際
- 年齢、体力などによって勧められる運動は異なります。
- まだ若く、骨密度が高く、骨粗鬆症予防を目的とする場合
- エアロビクス、ジョギング、テニス、バスケットボールなど
- 骨密度の低下が始まる年代の場合
- 急に激しい運動はかえって痛みの原因となります
- ウォーキングなどから始めましょう
- 膝や腰が痛い場合
- 関節への負担を減らすため、プールでのウォーキングがよいでしょう
 骨折は寝たきりの原因の第3位といわれています。骨折を防ぐには、骨を強くすることと、転ばないことが大切です。ここからは転倒予防についてお話しします。
骨折は寝たきりの原因の第3位といわれています。骨折を防ぐには、骨を強くすることと、転ばないことが大切です。ここからは転倒予防についてお話しします。
 転倒について
転倒について
- 統計データからわかること
- 65歳以上の家庭内事故の約7割は転倒事故
- 加齢に伴い、屋内での転倒発生件数が増える
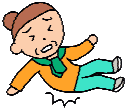
- つまずいて転ぶ高齢者が多い
 転倒の要因
転倒の要因
- 歩き方の問題
- 小刻み歩行、ちょこちょこ歩きでは転びやすくなります
- 住まいのつくりの問題
- 住み慣れていると気づきにくいかもしれませんが、つまずきやすいところや、滑りやすいところがあると思われます
 転倒がどんなときに起きているか
転倒がどんなときに起きているか
 転倒の発生場所
転倒の発生場所
- 高齢者では自宅での転倒が意外と多いことがわかっています
 転倒の危険因子
転倒の危険因子
- 筋力低下
- 下肢筋力の低下
- 足の筋力が低下するとバランスを崩したときに支えきれなくなって転倒しやすくなります
- 歩行能力の低下・障害
- 移動能力制限
- ベッドからの移動、トイレからに移動などの際に転倒する原因となります
- 末梢神経障害
- バランス障害
- 歩行障害認知障害
- 視覚障害
 転倒予防のための運動
転倒予防のための運動
- 正しい歩き方でウォーキング
- ストレッチ
- ふくらはぎ、太ももの裏側、背中、足の付け根などの筋肉を伸ばすと柔軟性がよくなり、とっさのときの反応がよくなります
- つぎ足歩行
- 右足のつま先に左足のかかとをつけ、次に、左足のつま先に右足のかかとをつけて歩く、という歩き方で約5メートルの歩行練習をするとよいといわれています
- 片足立ち
- はじめはどこかにつかまりながら、30秒間の片足立ちをしましょう
- 足指の運動
- 足指でグー、チョキ、パーをしましょう
- 外反母趾の予防にもなります

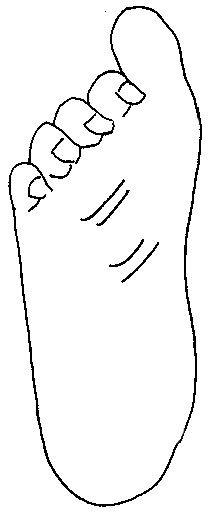
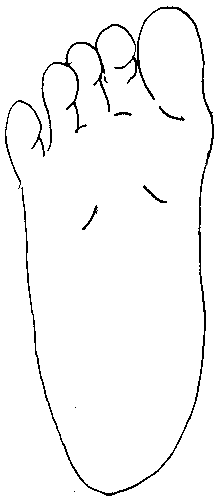
 正しい歩き方
正しい歩き方
 転倒予防のための環境整備
転倒予防のための環境整備
室内でも転倒事故が起こっています。慣れているはずの場所で、意外なものにつまずきます。敷居のちょっとした出っ張りやカーペットや座布団などにつまずいたりすることがあります。
- マットやじゅうたんを固定しましょう
- 敷居にスロープを作りましょう
- 階段に手すり、滑り止め、足下灯をつけましょう
- 浴室に手すり、滑り止めをつけましょう
- 歩くときに何かにつかまるとき、それが不安定なものでないか確認してからつかまりましょう
今回のお話が、皆さんの骨を強くし、転倒の予防につながり、骨折を防いで、元気に過ごされることの助けになれば幸いです。
<参考文献>
- 骨粗鬆症財団「丈夫な骨でいきいきライフ」
- Osteoporosis Japan別冊 vol12, No 1, 2004、「転ばないからだづくり」と「安全な住まいづくり」のコツ
- 骨粗鬆症と関節痛の総合サイト、RICH BONE:転びやすさ度チェック、転ばない住まいチェックは一度試しては、Q&Aも充実しています
- 武田薬品のホームページの中の、骨粗鬆症のはなし:骨粗鬆症危険度チェックが載っています
- 萬有製薬のホームページの中の、骨粗鬆症基礎編:年齢と体重から骨粗鬆症の危険度チェック、動画によるエクセサイズ等が参考になります
- 旭化成ファーマのホームページの中の、骨粗鬆症についてのページ:カルシウムクッキングメニューが豊富で参考になります
![]() 本日の予定
本日の予定![]() 骨粗鬆症とは
骨粗鬆症とは![]() 脆弱性骨折とは
脆弱性骨折とは![]() 骨の健康度チェック
骨の健康度チェック![]() 骨密度の変化
骨密度の変化![]() 骨密度からみた骨粗鬆症
骨密度からみた骨粗鬆症![]() 骨はどうして弱くなるのでしょうか
骨はどうして弱くなるのでしょうか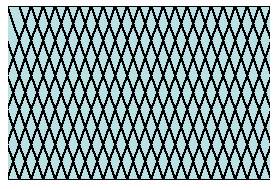
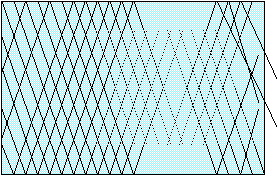
![]() どんな場合に骨は弱くなるのでしょうか
どんな場合に骨は弱くなるのでしょうか![]() 骨粗鬆症の危険因子として次のようなものがあります
骨粗鬆症の危険因子として次のようなものがあります![]() 骨粗鬆症、骨折予防のために
骨粗鬆症、骨折予防のために![]() まず、食事のポイントについてみていきましょう。
まず、食事のポイントについてみていきましょう。![]() 一日のカルシウム摂取量
一日のカルシウム摂取量![]() カルシウム
カルシウム
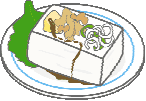

![]() ビタミンD
ビタミンD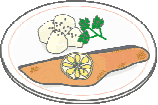
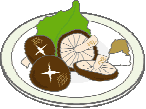
![]() マグネシウム
マグネシウム
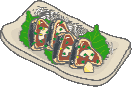
![]() 塩分について
塩分について![]() アルコール、喫煙について
アルコール、喫煙について

![]() 運動について
運動について![]() 運動の骨粗鬆症予防効果
運動の骨粗鬆症予防効果![]() 運動療法の実際
運動療法の実際![]() 骨折は寝たきりの原因の第3位といわれています。骨折を防ぐには、骨を強くすることと、転ばないことが大切です。ここからは転倒予防についてお話しします。
骨折は寝たきりの原因の第3位といわれています。骨折を防ぐには、骨を強くすることと、転ばないことが大切です。ここからは転倒予防についてお話しします。![]() 転倒について
転倒について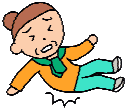
![]() 転倒の要因
転倒の要因![]() 転倒がどんなときに起きているか
転倒がどんなときに起きているか![]() 転倒の発生場所
転倒の発生場所![]() 転倒の危険因子
転倒の危険因子![]() 転倒予防のための運動
転倒予防のための運動
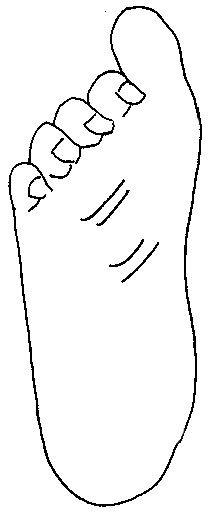
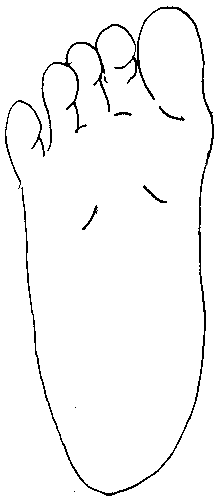
![]() 正しい歩き方
正しい歩き方![]() 転倒予防のための環境整備
転倒予防のための環境整備![]()